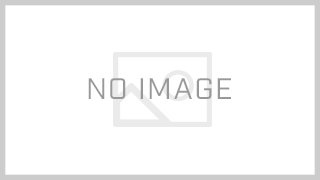第一第2話 同人(玄敏僧都)、伊賀国の郡司に仕はれ給ふ事
伊賀国のある郡司のもとに、身なりの卑しい法師が、「やとってください」と、そっと入ってきた。郡司はこれを見て、「あんたのような坊主を置いても何にも役に立たない。特に必要なことはない」と言った。それに対し法師はこう言った。「私ほどの身分の下の者は、法師といっても普通の下男とかわることはありません。どんな仕事でも、できることはやります。どうか雇ってください」と。すると郡司は「そこまでいうなら、まあいいだろう」と言って彼を留めた。その法師はとても喜んで真面目に働くので、郡司は特に大事にしている馬を法師に預けて面倒をみさせるようになった。

こうして、三年ほど経ったある日、この郡司の男が上司である国司のために、やや都合の悪いことをなしてしまって、国外に追放されることになった。彼は父や祖父の時代から居ついていた人であり、所領も多く、家族も多数いた。他の国へ逃れることは危険だとわかっていても、どこにも逃げる場所がなく、悲しみながら立ち去ろうとしたとき、この法師が家の或者に向かって「こちらの殿様は、どのような悲しみが起こってこのようなことになっているのですか」と法師が尋ねると、或者はこう言いった。「お前ごときの賤しい者が聞いてもしようがなかろう。」と、けんもほろろにこたえるのを「なんで身分が低くても無関係のはずがありましょうか。雇っていただきお世話になって数年経ちました。差別なさるのは不都合です、」といって丁寧に問えば、仔細をありのままに或者は語った。法師は次の様に言った。
「私が申し上げることは、お取り上げになりますまいが、どうしてこのように急いで立ち去る必要がありましょうか。物事はときに思いがけないことも起こるものです。まず京都へ行って、いくたびか当方の実情も申し述べて、それでも致し方なければ、その時にこそ、どこにでも行かれるとよいでしょう。私が少しばかり知っている人も、国司では心当たりが複数ございます。尋ねてみて、実情を申してみましょう」と。
人々は見かけによらずすごいことを言うものだと不思議に思ったが、郡司にこの話を報告した。郡司は法師を近く呼び寄せて、自ら尋ね聞き、真剣に彼に頼むこともなかったが、他にあてもないので、この法師を連れて京都へ向かった。
その時、この郡司の国は大納言なにがしかの命のもとで国司が統治していた。
京都に着いた法師は、その郡司に頼んで、こう言いった。「人を尋ねようと思うのですが、このようなみすぼらしいなりでございます。衣服や袈裟をお借りできませんか」と。するとすぐに借り物の衣服を着せられた。
郡司の男を連れて、彼を門に置き、中に入って法師は「話があります」と言った。すると人々は集まってきて、彼を見て驚き、ひざまずいて敬意を表した。伊賀の男つまり郡司は門のそばからこれを見て、仰天した。「なんということだ!」と見守っていた。
すぐに事情を聞いて、大納言は法師に出て会いに行った。大納言は彼をもてなし、騒ぎ立てる様子はまったくもって特別のものだった。大納言は「さて、出奔されてどのようになったのか、と想像する手掛かりもないまま年月が経つばかりでございましたが、まぎれもなくあなたがおいでになるとは!」と、思いのありったけをしきりにのべたてた。それに対して玄敏法師は言葉を少なくして、「そのことについてはいずれゆっくりお話しましょう。今日は、特に話すべきことがあるのです。伊賀の国で私が頼んで世話になっていた者が、思いもしないお咎めを被って、国外に追放の沙汰となって嘆いているのです。気の毒に思いますので、もし、深刻な罪を犯していないのであれば、この法師に免じて許しを与えていただけませんか?」と言った。「あれこれ申すまでもないことです。あなたが好意を持つほどの人物であれば、処罰されなくても自分でその罪の自覚をできる男なのでしょう」と大納言は言って、これまで以上に待遇する内容の庁宣(行政命令)の下付を法師が伝えたので、大納言は喜んで新たな命令を出した。これにつき 伊賀の男 郡司が驚き惑う様子ももっともなことだった。
郡司はいろいろと考えたが、あまりのことに適当なお礼の言葉も出ないで、「宿に戻って落ち着いてお礼を申し上げよう」と思っていた。玄敏法師は、借りていた衣服や袈裟の上に庁宣をおいたまま、立ち去った。そのまま、どこへともなくお隠れになったということである。
これもまた、玄敏僧都のなされたことである。まことに稀有で有り難い心であった。
(20230628訳す)