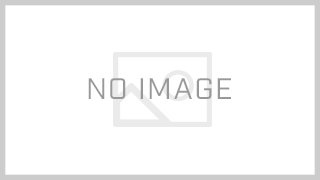第一第10話 天王寺聖、隠徳の事 付、乞食聖の事(てんのうじひじり いんとくのこと こつじきひじりのこと)
近頃、天王寺にはある聖(ひじり)がいたという。彼は話すときに常に「瑠璃(るり)」という二文字を語尾に付け加えて話す独特な癖(くせ)があった。だから、その文字を名前に付けて「瑠璃」と呼ばれるようになった。

彼の姿は、布をつぎはぎしたのや、紙で作った衣装で言いようもなく破れてぼろぼろになったものであった。たくさんのこうした布切れで着ぶくれしていた。そして、乞食して集めた物を一つの袋に入れて、その姿でうろつきながら食べていた。
子供たちが大勢集まって彼を見て笑ってはやしたてるが、特にこれを咎(とが)めたり、怒る様子もなかった。たとえ子供たちが彼のことをひどくいじめるときでも、例の乞食して集めた食べ物のはいった袋から物を取り出して勘弁してもらおうと渡そうとするのだが、こどもたちは汚(きた)ながって受け取ろうとしない。
結局こどもがこれを捨てるとまた取って拾って袋に入れ戻した。一方で、いつも他愛もない様々な言葉を口にしながら、ただただ狂人のように振舞っていた。
彼は特に一つ所にとどまる様子もなかった。垣根や木の下、土塀(どべい)に沿った地べたで寝て夜を明かしていた。
同じころ、四天王寺の東南の大塚という地に貴(とうと)い高僧がいた。
ある雨の夜、
「雨が降っていて、行くべき場所もないので、この縁側の隅にお邪魔しまするり~」といいながら天王寺の瑠璃聖(るりひじり)がこの高僧の居所(きょしょ)にやってきた。
高僧は普段の習慣に反し、不思議に思いながらそのまま起き上がった。
夜が更けてきて、瑠璃聖が言った。
「偶然ここに立ち寄りお伺いしましたるり~。長年疑問に思っていたことなどを、お教えいただきたいと思うるり~。」と。
高僧は彼の狂人のような話し方や乞食(こじき)のような外見から意外に思ったが、普通の僧に対するように相手になって話し込んだ。話は進んで、天台宗の教理の深義(じんぎ)などが瑠璃聖から尋ねられた。そして、高僧である主(あるじ)は驚き、珍しいと思いながらも、夜通し寝ずにさまざまな質問と答えを聖(ひじり)との間に繰り返した。

そして、夜明け頃になった。「もう今夜はお暇(いとま)させていただきまするり~。長年 疑問に感じていた教理の上の種々のことがらが、今晩お邪魔し、お伺いして氷解(ひょうかい—疑念が解ける)しましたるり~。来てよかったるり~。」と言って瑠璃聖は去っていった。
さて、以上の出来事をありがたく尊く思い、周囲の人々に かの高僧は話した。
するとそれを伝え聞いた人々やこどもたちは瑠璃聖をバカにしたりいじめたりするのを改めた。
以来一部の人達は 瑠璃聖のことを衆生を救済すべくこの世に現れた権現(ごんげん)のように崇(あが)めるようなこともあった。しかし、当の本人の様子は以前と少しも変わることがなかった。
「そんなことがあったのですか?」と人々に高僧とのやり取りを尋ねられると、
「そんなことは ないるりよ~~~」と、
瑠璃聖は笑って冗談めいた言葉で話を遮(さえぎ)ってしまうのだった。
こうして、人々に知られて過ごすことを面倒に思ったのだろう。ついに行方(ゆくえ)も知らせず聖(ひじり)は其処(そこ)から立ち去っていなくなってしまった。
年を経て、天王寺のとなりの和泉国(いずみのくに)で聖は乞食(こつじき)しさまよい歩いていた、と。
そして、最後には人々も近づかない場所の大きな木の下で、小枝に仏画を掛けて西を向いて合掌し、目を閉じて往生されていた、とのことである。臨終の際は誰も知らず、その姿は後に見つけられたという。
また、これも近頃 仏名(ぶつみょう)と呼ばれた乞食(こつじき)の聖もいた。
彼も 天王寺の瑠璃聖(るりひじり)のように、物に狂ったような振る舞いをしていた。食べ物は魚や鳥さえも嫌がらなかった。衣服は筵(むしろ)やぼろぼろの菰(こも)を重ね着して、まともな人の姿に見えなかった。
出会う人々に必ず「尼人(あまびと)、法師(ほうし)、男人(おとこびと)、女人(にょにん)の皆様は皆 仏性(ぶっしょう—ほとけになる可能性)があって、清浄(しょうじょう)なーーり」などと言って拝む仕草を行っていた。
だから彼の名を仏名(ぶつみょう)と言ったのである。
彼のことを見る人は皆、愚かで気味が悪い乞食だとのみ思っていた。しかし実に人は外見からはわからないものである。
高徳で人に知られた阿証房(建礼門院けんれいもんいんの戒師かいし と平家物語に記録あり)という聖を かの乞食聖は親友に持っていた。余人(よじん)が到底理解できないような経典や論書などをこの乞食聖(こつじきひじり)は親友の阿証房から借りて読んでいた。借りた文章を人に知られずに懐(ふところ)の中に入れて持ち歩き、時を経て読了したものを阿証房に返すといったことを習慣としていた。臨終は 高野川の東岸の堤(つつみ)の上で西を向いて端座して合掌し往生(おうじょう)されたということである。

今回、私鴨長明が紹介した二人は、六道世間を乗り越えて九の覚醒を目指したアウトサイダ-の最高の形態の具現者である。
『白氏文集』(はくしもんじゅう)に「大隠(だいいん)は朝市(ちょうし)にいる」—(真の隠者(いんじゃ アウトサイダ-)は、市井(しせい)の喧騒のなかにこそいる)とあるのは、まさに今回紹介の二人にあてはまるのである。
「大隠は朝市にいる」という言葉の心は、次のとおりである。
真の賢者が六道の世間に背を向ける傾向性から彼はアウトサイダ-にならざるを得ない。しかも、我が身を六道世間のただなかに置きながら、それを乗り越えようとする真の心と自ら有する徳を隠して、市井の人々のただなかで生きるのが最高の在り方なのである。
この隠徳(いんとく)のアウトサイダ-が、六道世間の市井(しせい—街中)で生きていくという形態は最高であるだけに実践は非常に困難である。
同じアウトサイダ-でも、山林の中に分け入り行方(ゆくえ)を隠す形態の者は、市井にあって自分の徳を隠すことのできない初歩の者(ビギナ-)であるのかもしれない。
無論 山林に逃れ小さな方丈(ほうじょう 移動式の庵)に住居を有する私 鴨長明もこのビギナ-に過ぎない。
(20230711訳す)