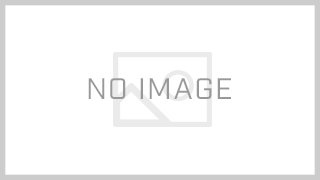発心集 第一
第一第1話 玄敏僧都、遁世逐電の事(げんひんそうづ とんせいちくでんのこと)
昔、玄敏という僧がいた。彼は山階寺(やましなでら)の非凡な知者であったが、世間を嫌う気持ちが強く、少しも他の僧侶との交際を好まなかった。三輪川のほとりにわずかな草庵を結び、ひっそりと住んでいた。
桓武天皇の時代に、その存在が知られ、無理矢理に召し出されることとなった。逃げる場所もなく、仕方なく参上した。
しかしながら 本意ではないと思ったのであろうか、次の奈良の天皇の時代に大僧都に任命せられたことを辞退するうたを詠んだ。
三輪川の清き流れにすすぎてし衣の袖をまたはけがさじ
(三輪の河原の草庵で隠遁生活を送るこの身を、ふたたび世俗に交わって汚す気はない)
とのうたをたてまつった。
彼は弟子や側近にも知られずに消えてしまった。いずこともなく出奔してしまった。探し求めたが見つからない。捜索のかいもなく何日も経過したが、彼と縁のあった人はもちろんのこと、他の人もすべていなくなった彼のことを惜しみ嘆いていた。
その後、年月が経ち、弟子であった人物が用事があって越後へ向かう道中のある所で、大きな川があった。彼が舟待ちして乗ろうとした時、渡し守を見ると、頭は髪の毛が掴めるほどに伸びた法師が汚い麻の衣を着ていた。
「どうしたことだろう」と思いながら、やはり見覚えのあるような感じがしたので、「誰かに似ている」と考えているうちに、失せてしまってから長い年月が経っていたわが師の僧都であると思いいたった。「人違いでないか」と見たが、まごうことなく師であると弟子は確信した。とても悲しくて、涙のこぼれるのも抑えつつなにげないふりをしていた。
その渡し守も気づいている様子であるが、決して視線を合わせようとはしない。弟子は 走り寄って「なぜこんなところにおいでなのですか」とも言いたかったが、たいそう人が多くいたので、「今はかえって人目について具合が悪いだろう。都への上りの帰り道で いらっしゃりそうな場所に師を尋ねていって、ゆっくりごあいさつしよう」と思って、弟子はその場は去ってしまった。
かくてその後、帰途に 弟子がその渡し場に戻ると、師とは別人の渡し守がいた。目の前が暗くなり、胸が締め付けられるおもいを感じながら、詳しく尋ねると、「その法師は以前ここで渡し守をしていらっしゃいました。長年、ここの渡し守として勤めていましたが、そんなに身分が下の者とも思えない様子でした。いつも落ち着いた様子で念仏を唱え、多くは船賃も取らず、ただそのとき食べるもののほかは欲張る心もなく勤めておりました。この地の人々も非常に彼を大切にしていましたが、何があったのでしょうか、あるとき突然消え失せ、行方が分からなくなりました」と語った。それを聞いて、残念に思い、その日付けを数えれば、その弟子が彼に会った時の月日と一致した。「自分の身の様子を知られまい」と師は再び去ってしまったのである。
この話は物語にも書かれている。私は人々の語るあらましをざっと書くだけである。
また、古今の歌に、
「山田もる僧都の身こそあはれなれ秋はてぬれば問ふ人もなし」
(山の田を守る そほづ(案山子の古語 僧都とかけた)の身を思うとしんみりとする。秋が過ぎると だれからも忘れられる存在となるからだ。)とある。
これも玄敏のうたである。雲や風のようにさまよい歩いた彼は、田畑を守ることもあったのだろう。
おなじころ、三井寺の道顕僧都といわれる人がいた。玄敏の物語を見て、涙を流しながら、「渡し守こそ本当に罪のない、世を渡るための道なのだ」と言い、琵琶湖の方に舟を設けたということだった。
この話は計画として語られるだけであり、その設けられた舟はむなしく石山(琵琶湖のほとりのまち)の河岸に消え朽ちてしまったが、私は彼の思いそのものは貴重なものであったと思っている。
(20230625訳す)